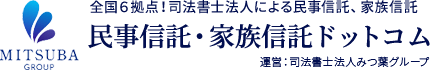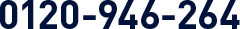民事信託の基礎知識
受益権の贈与と売買
信託契約における受益権の基本知識と一般形態
信託を活用した場合、信託財産から発生する経済的な利益を受け取れる権利、つまり受益権を受益者は保有しています。
信託法や信託業法に則り、定められた契約内容に従って、受託者には一定の義務・責任が発生してきます。
そして、受益権は、債権の一種なので、贈与することも売買することもできます。
注意が必要な不動産における信託受益権売買とは?
不動産を信託財産として活用される方が増えています。
しかし注意をしておかなければならないのは、不動産の信託受益権は取引上、株式や債券などと同様に有価証券として取り扱われることです。
実物の不動産と、不動産の信託受益権の売買では、取引の内容が異なるという認識が必要です。関連してくる法令も宅地建物取引業法ではなく、金融商品取引法へ代わります。不動産会社の方が仲介をする場合は、金融Ⅱ種免許が必要になります。
信託受益権の評価方法と時間経過に伴い変化をみせる価値
少し応用編です。
信託における受益権は、「元本受益権」と「収益受益権」から構成されています。
株式や債権、不動産などの「元本部分」と、賃料収入や配当、利息などを受け取る「収益部分」に分離されます。
そのため元本受益者と収益受益者が異なる場合には、これらの権利は分離して評価されます。
そのため時間の経過とともに減少する「収益受益権」の評価と、時間の経過とともに上昇をみせる「元本受益権」の評価に着目したのが、受益権分離型信託といえます。
親が収益受益権を、子が元本受益権を持つことにより、時間の経過とともに財産移転を行うことができます。
また信託期間が終了すれば、信託された財産は、所有者である委託者の元へ戻されます。
そのため贈与税の支払いを少なく抑えながら、相続税の減税効果が期待できます。親の生存中に資産の移転が完了するため、税金対策としても有効な手段として注目を集めています。
関連記事
-
- 民事信託の基礎知識
後見制度支援信託とは? 商事信託と民事信託は、必ずしも競合するものではありません。活用事例①の共有不動産の解消、活用事例②贈与信託の場合は、民事信託で達成できます。しかし、商事信託でしか実現できないものもあります。例えば、後見制度支援信託があります。ご紹介しましょう。
後見制度支援による信託を活用した財産管理の方法とは?
そもそも後見制度とは、法定後見と任意後見に分かれます。成年後見制度とは、認知症や知的・精神障害などによって本人に判断能力がない場合に、成年後見人を選任することで法律的に本人を支援していく制度です。
後見制度支援信託とは、上記のように支援を受けている方の財産管理を、信託という手段を利用して行うものです。
そのため契約や変更、解約などの手続きは、すべて家庭裁判所の指示に基づいて行われます。
本制度においては、本人が日常生活に必要とする金銭以外を、信託銀行などに信託として預けることで、後見人などによる財産横領を防ぐことができます。家庭裁判所への手続きが必要となる信託契約締結の流れとは?
後見制度支援信託を利用する際には、まず家庭裁判所への後見開始の申立てを行います。裁判所が当該支援信託の利用検討の余地があると判断した場合には、司法書士などの専門家を後見人に選任します。その上で、本人の生活や財産の状況をトータルに考慮し、専門家の後見人による検討・判断が行われます。
そして信託制度を利用すべき場合には、家庭裁判所へ作成した報告書の提出を行います。そして裁判所から発行された指示書をもとに、信託契約を締結します。
後見制度支援信託を利用することで防げる不正行為
親族後見人による、財産の使い込みは年々増加を続けています。平成23年~24年の計2年間では900件以上、被害総額は80億円を超えています。後見人によって財産を横領する事件が起きれば、財産を損なうという直接的な被害だけではなく、成年後見制度自体の信頼性が問われてきます。
しかし、後見制度支援信託であれば、信託契約締結後は、契約で定められた金額のみを、定期的に後見人の管理している口座へと送金します。そのため、日常的な支出のみを実質管理をする形になります。もちろん医療費などの予定外の支出があれば、裁判所からの指示を得て、契約内容を変更することが可能です。
- 民事信託の基礎知識
-
- 民事信託の基礎知識
信託監督人と受益者代理人ってなに? 信託と成年後見制度における「受益者」と「後見人」の立場の違い
成年後見制度においては、家庭裁判所によって監督を受けなければなりません。(任意後見制度の場合は、後見監督人が必須になっています。)そのため裁判所によって、成年後見人として妥当だとされる人物が選定されます。弁護士や司法書士、社会福祉士、税理士といった専門家が選ばれることが多いですが、家族や友人が選任されるケースもあります。
しかし家族信託においては、監督機関はありません。そこが家族信託の魅力でもあり、リスクのひとつでもあります。信託の場合は、信託監督人を置くことが可能になるというレベルです。利益を受け取れる人「受益者」のために、財産を託される「受託者」が運用・承継を行っています。通常は、受益者が受託者を監督しています。しかし、信用のおける信託財産を管理・運用をきちんと行っているのか、受益者が監督できない場合を想定し、信託監督人を設けることが一般的です。信託監督人は、司法書士等の専門家をオススメします。
根本的な財産管理方法が異なる2つの方法
成年後見制度においては、家庭裁判所へ定期的な財産管理の報告が必要になります。そのため財産の処分となれば、裁判所の許可が必要になります。
一方、家族信託では、原則的に受益者が、受託者を監督します。成年後見制度よりも、自由に財産を動かすことができるため、信託監督人や受益者代理人などを置いて監督するケースもあります。
被後見人を受益者としている場合には、親族後見人に月々定額の生活費を給付することで、不透明な財産管理を減らす役割も期待できます。受益者代理人を置くことで、受益者の代わりに意思表示することが可能になります。最近では親族後見人による横領や浪費事件が増えているため、監督機能は特に注目が集まっています。
信託監督人や受益者代理人の存在
家族信託において、受託者に選ぶ人物には、絶大な信頼をおけることが絶対条件です。大切な財産を託すことになるため、受託者選びは非常に重要となってきます。
しかし、受益者が高齢化し、判断能力が衰えてきた場合、委託者の意向を守り、受益者の利益を守るために、信託監督人や受益者代理人という存在は必要になってきます。
家族信託のすべての契約に、信託監督人や受益者代理人が必要なわけではありません。受益者代理人は受益者と同等の力を持つことになります。設定する際は、慎重に検討しましょう。
- 民事信託の基礎知識