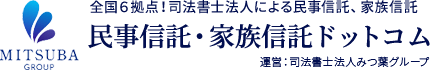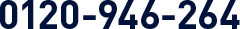民事信託の基礎知識
信託を活用すると税金が発生するパターンとは?
家族信託を活用する際には、税金を考える必要があります。最終的な税務リスクは顧問の税理士や税務署へご相談ください。ここでは、一般的な信託に関する税金のお話しをしましょう。
信託財産に不動産が含まれていると、所有権移転登記が行われるため、登記簿に受託者の氏名が記載されます。しかし、登記簿上の所有者が形式上、受託者に名義変更がなされただけでも、税金が課税されるのでしょうか?
信託設定時における税金は二つの考え方があります。
①自益信託
まず、「委託者」=「受益者」が同一人物であるのかないのか、が問題となります。
「委託者=受益者」の場合には、受益者は利益を受けている訳ではないので、贈与税は課せられません。
②他益信託
委託者≠受益者の場合、つまり両者が異なる場合には、みなし贈与とみなされて贈与税が課せられます。
また、どちらの場合にも、課税されるのが、所有権移転登記の手続き時に発生する登録免許税です。
そして受託者への不動産取得税は、形式的な所有権移転のため発生しません。
同時に、委託者への譲渡取得税も利益発生が起こらないため課税されません。
では、受託者に課税される税金はあるのか?
それは、毎年1月1日の不動産所有者に課せられる固定資産税です。形式的に所有者になるため、受託者に固定資産税が課税されます。しかし、実質的には信託財産の中から実務として受託者が支払いをするため、負担者は信託財産から支払うケースが多いです。
関連記事
-
- 民事信託の基礎知識
家族信託を設計してみよう この章では、実際に信託を活用する際の流れをご紹介します。
次の項目をお考え頂いた上で専門家へご相談頂くと、スムーズにお話ができるのではないかと思います。どうやって決めればいいか分からないという場合は、相談しながら決めていけば良いでしょう。
(1)目的を明確にする
何より大事なのは、皆様がご自身の財産をどうしたいのかという「想い」ですから、その「想い」を明確にしていく作業から始まります。まずは、次のチェック項目の中にご自身に当てはまるものがあれば、チェックを入れてみてください。
□ 自分が元気なうちに財産の分け方を決めておきたい
□ 相続人の遺産分割協議がまとまりそうにない
□ 財産の管理を誰かに任せたい
□ 認知症が心配
□ 近い将来不動産の処分を考えている
□ 複数人で共有している不動産をどうにかしたい
□ 二次相続以降に不安がある
□ 会社を後継者に引き継ぎたいが方法が分からない
□ 先祖伝来の不動産は代々引き継いでほしい
□ 自分の死後、生活が心配な相続人がいる(障がいをお持ちの方など)
□その他( )(2)当事者を誰にするか
次に、それぞれの役割を担ってくれる方がいらっしゃるか、誰に財産を引き継いでいきたいかを考えていきます。
委託者:皆様ご自身
受託者:
第一次受益者:
第二次受益者:
第三次受益者:
※委託者と受益者が異なる時は、贈与税が発生します。
□ 信託を監督する人を設けたい → 信託監督人:
□ 自分に代って受益権を行使してくれる人を決めたい → 受益者代理人:
□ 受益者に指定した人が適切に受益権を行使するのが難しい(認知症・未成年・精神上の障がいなど)
→ 受益者代理人:(3)何を信託するのか
相続対策の手順に従って、まずは財産の棚卸しをして下さい。その上で、信託する財産を決めていきます。□ 不動産
□ 現金
□ 株式
□ その他( )
(4) 信託の始まりと終わり
信託をいつから、いつまで継続させるのかを決めます。信託の始まり
□ 今すぐにでも始めたい
□ 自分が認知症になったら
□ 自分が亡くなってから
□ その他( )信託の終わり( )
- 民事信託の基礎知識
-
- 民事信託の基礎知識
受益権の贈与と売買 信託契約における受益権の基本知識と一般形態
信託を活用した場合、信託財産から発生する経済的な利益を受け取れる権利、つまり受益権を受益者は保有しています。
信託法や信託業法に則り、定められた契約内容に従って、受託者には一定の義務・責任が発生してきます。
そして、受益権は、債権の一種なので、贈与することも売買することもできます。注意が必要な不動産における信託受益権売買とは?
不動産を信託財産として活用される方が増えています。
しかし注意をしておかなければならないのは、不動産の信託受益権は取引上、株式や債券などと同様に有価証券として取り扱われることです。実物の不動産と、不動産の信託受益権の売買では、取引の内容が異なるという認識が必要です。関連してくる法令も宅地建物取引業法ではなく、金融商品取引法へ代わります。不動産会社の方が仲介をする場合は、金融Ⅱ種免許が必要になります。
信託受益権の評価方法と時間経過に伴い変化をみせる価値
少し応用編です。
信託における受益権は、「元本受益権」と「収益受益権」から構成されています。
株式や債権、不動産などの「元本部分」と、賃料収入や配当、利息などを受け取る「収益部分」に分離されます。
そのため元本受益者と収益受益者が異なる場合には、これらの権利は分離して評価されます。
そのため時間の経過とともに減少する「収益受益権」の評価と、時間の経過とともに上昇をみせる「元本受益権」の評価に着目したのが、受益権分離型信託といえます。親が収益受益権を、子が元本受益権を持つことにより、時間の経過とともに財産移転を行うことができます。
また信託期間が終了すれば、信託された財産は、所有者である委託者の元へ戻されます。そのため贈与税の支払いを少なく抑えながら、相続税の減税効果が期待できます。親の生存中に資産の移転が完了するため、税金対策としても有効な手段として注目を集めています。
- 民事信託の基礎知識