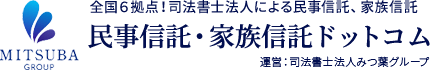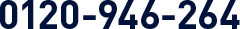民事信託の基礎知識
どんな財産を信託することができるのか?
所有者が保有している財産は、固有財産と呼ばれます。
では、どのような固有財産が信託することができるのでしょうか。
原則として、“財産的価値があるもの”は、信託することができます。
①不動産所有権、借地権、動産(ペット)、金銭
*信託契約により、管理・処分権限が受託者へ移ります。
②上場株式、非上場株式、著作権や知的財産権
*財産権以外の、議決権や利用決定権は受託者へ移ります。
③債権(請求権)、将来債権(未実現の請求権)
信託することができないもの
次のものは、信託できません。
①生命、名誉
②債務、連帯保証(いわゆるマイナス財産は信託できません)
③一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)
なお、注意点としては、信託契約書に銀行口座を記載される方がいらっしゃいますが、銀行口座は、預金債権です。通常、銀行の預金債権は譲渡禁止特約付債権になります。
したがって、預金債権は信託できません。
また、債務は信託できない財産ですが、別途、債務引受はできます。実質、債務を信託することと同じ状態にすることができます。
関連記事
-
- 民事信託の基礎知識
委託者、受託者、受益者が死んだら? 信託契約における当事者が死亡した場合、誰が権利を継承するの?
信託契約には、「委託者」「受託者」「受益者」の3つの立場が存在します。そのため当事者が死亡した場合には、それぞれの定めに従って相続が行われます。
3つすべてに共通して言えることは、信託の契約内で、当事者の死亡時の次の継承者を決めてあれば、その内容に従うことができます。
そのため財産を継承させたい場合には、信託契約にその旨の内容を明記しておく必要があります。
立場別に見る「委託者」「受託者」「受益者」の権利承継者
まずは委託者が死亡した場合、委託者の地位が相続によって継承します。
そこで、以下のような文言を記載します。
(委託者の死亡後の委任者の権利)
第○条 委託者の死亡により、委託者の権利は消滅するものとする。しかし遺言による信託を行った場合には、相続人には委託者の地位は承継されないように信託法で規定されています。
そして受益者が死亡した場合も、委託者同様に、財産の相続人が受益権を相続することで受益者となります。信託契約内に明記がなければ、遺産分割協議で他の財産と同様に取得者や取り分が決められます。生前に受益者が相続人指定をしておくことも可能です。ちなみに、受益権の財産評価は、通常の財産評価と何ら変化はありません。したがって、不動産建物は固定資産税評価額、土地は路線価です。つまり、信託を活用することで直接的な相続税の節税には繋がらないのです。
最後に受託者が死亡した場合ですが、次の受託者を選任しなければいけません。信託契約内に選任方法が明記されていればその方法に従います。定めがない場合には、委託者と受益者が話し合い、合意のもとで新しい受託者を選びます。話し合いがまとまらない場合などにおいては、裁判所に申し立てをして選任をしてもらうケースも出てきます。
信託契約の終了を左右してしまう受託者選任の重要性
注意が必要なのが、受託者が死亡して1年間、次の受託者が選任されなかった場合、強制的に信託契約は終了してしまうということです。(1年ルール)
そして受託者の相続人は、受託者の地位を相続して承継することはないものの、新しい受託者が選任されるまで、信託財産を管理する立場にあります。
そのため信託契約を締結する段階で、さまざまな事情が起こった際の対処法を想定しておかなければなりません。
受託者が死亡した際、次は誰を受託者に指名するのかは最低限、決めておくべき事項になります。誰が先に亡くなるのかは、誰にもわからないことです。そこで、あらゆるケースを想定し、対応策として先手を打っておくことが信託契約の成功の鍵となってきます。
- 民事信託の基礎知識
-
- 民事信託の基礎知識
信託が終了するときのコストと流れ 信託契約が終了すると行われる清算手続きとは?税金はいくら?
信託契約の終了事由に該当した場合、清算の手続きが行われます。終了だと判断された時点における信託財産に属する債務弁済を行った上で、財務財産を契約上に定められている帰属権利者へ引き渡します。
信託契約において、疑問点として多く挙がるのが税金の問題です。家族信託が終了した場合、「受益者=財産の帰属権利者」であるのか「受益者≠財産の帰属権利者」であるのかにより税金の有無が変わってきます。
信託終了時の受益者と信託財産の取得者が同じ場合、実質的な財産の移転はないため贈与税や相続税は発生しません。
しかし終了時の受益者以外が信託財産を取得した場合には、贈与や相続と判断され、残余財産の取得者に贈与税や相続税が課せられます。
信託契約終了において最も重要とされるのは元本受益権
信託契約の最終的な目的は、信託契約の終了によって、元本が指定の受益者に引き継がれることにあります。
そのため当然のことながら、終了時点においての元本受益部分に対する税金を最大限に考慮しておかなければなりません。相続を原因とする信託契約内容の遂行であれば遺贈になりますが、期間満了など他の要因による終了の場合、委託者が受益者と同一でない限り、贈与税が課税されてしまいます。
もちろん、不動産の場合は、不動産取得税も課税されます。ご存知の通り、贈与税の税率は高く、納税者の負担が大きくなります。
そこで終了時における最終取得者に、大きな負担を強いてしまうような契約内容は避けなければなりません。
そのため、家族信託の残余財産の取得者に負担をかけずに継承させる税金対策を講じておかなければならないのです。長期間に渡る、後継ぎ遺贈型受益者連続信託は、委託者にしてみれば確かに安心かもしれません。
しかし、最終の着地点を見誤ってしまうことで、残余財産取得者に大きな負担を強いてしまうため、慎重な検討が必要になります。
- 民事信託の基礎知識