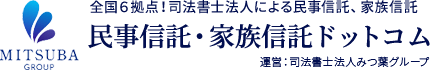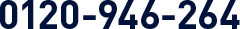民事信託の基礎知識
信託の方法は実は三種類ある!?
①契約信託
委託者と受託者との間で信託契約書を結ぶことで、信託がスタートする方法です。この信託契約書は、必ずしも公正証書にする必要はありません。ケースによっては公正証書にします。
ただし、公証役場で確定日付や認証は行うことをオススメします。費用は1通700円くらいです。
なぜ確定日付をいれるのか?
契約書はワードで作成しますので、データを改ざんされてしまうと、本当にその日に作成したのかが不透明になってしまうからです。つまり、税務署が税務調査をした場合、贈与や信託の日付が本当に正しいのか疑われないように対策するためです。公証役場にいる公証人が日付入りのスタンプを押すことは、税務署も疑いの余地がありません。
②遺言信託
委託者は、信託契約ではなく、遺言書の中に、「委託者が亡くなったら、信託を発生させたい。」というような中身を記載します。つまり、亡くなった瞬間に信託の効力が発動します。
さて、もしかすると、勘のいい方はお気づきかもしれませんが、違和感ありませんか?「あれ?遺言信託?どこかの銀行がやっていた名前と同じではないか」
そうなのです。銀行がサービス提供している商品に「遺言信託」があります。
実は、遺言信託は「信託」という名前こそ付いていますが、厳密には第三者に財産の管理を委ねる「信託」そのものではありません!あくまでもお客様が遺言書を信託銀行に預けて、信託銀行がその遺言書に基づいて遺言を執行することをいいます。つまり、遺言信託は「遺言文案+遺言保管+遺言執行」のサービス名称にすぎません。これを誤解しているお客様が非常に多いです・・・
金融機関がお話している遺言信託はどちらの意味なのかを分けて考えて頂く必要があります。
銀行の遺言信託では、二次相続以降の引き継ぎ先は決めることが出来ないので、大事なのは、ご自信がどういう想いで財産を残したいかですね。そして、遺言信託は公正証書ですることをオススメします。
③自己信託
ある日、自分の財産を信託します。という宣言をすることで信託を発動させる方法です。
つまり、委託者と受託者と受益者が同じ方法です。
これに関しては、公正証書で作成します。ただし、注意点としては、受託者と受益者が同一の状態が1年間続いた場合は、信託が終了するという1年ルールがありますので、受益者を複数にするのか、受益者の変更を行う必要があります。
関連記事
-
- 民事信託の基礎知識
自己信託とは? 平成20年より可能になった自己信託の概要とは?
自己信託とは、委託者自らが受託者となる信託のことをいいます。そのため信託設定後においても、本人が所有者であり管理者として、財産の決定権・裁量権を持っています。
なぜ、わざわざこのようなことをする必要があるのでしょうか?
それは将来、トラブルになってしまいそうな財産を自己信託しておくことで、受益者を指定しつつも、生きているあいだは自己の判断で自由に運用・管理することが可能になるからです。
しかし、旧信託法においては、自己信託という方法を認めてしまうことで、信託財産が倒産隔離されてしまい、執行免脱の恐れがあると考えていました。
ですが、欧米など海外でも広く認められ利用されている制度であるため、平成19年9月30日の改正信託法の施行を経て、平成20年9月30日に可能となったのが、自己信託という新しい財産管理方法です。
自己信託を行うことで手に入る大きなメリットとは?
自己信託という方法は、後継者に自社株を承継させる手段として非常に優れています。例え明確に後継者が決まっている場合でも、いきなり自社株を譲渡するのではなく、まずは自己信託を行います。
そうすることで、当事者である本人が管理者となって議決権を行使し、経営オーナーとして経営権を握ったまま、後継者への株式移転が行えます。この際には、受益者連続信託を行えば、後継ぎである子Aの死亡後には、孫であるBを受益者とする内容の指定も可能になります。
また。法人が新規事業に進出する場合でも、わざわざ子会社を設立させて出資を募らなくても、事業部門を自己信託してしまえば、資金調達が行えるなどのメリットも大きくなっています。
若しくは、財産管理会社を設立した後に、不動産を簿価譲渡することがあります。その際の方法として、一度自己信託を活用し、その後、受益権売買で法人へ移転させる方法があります。
懸念されていた倒産隔離への対策と締結時の注意点
自己信託の成立に向けて、大きな壁となっていたのが、倒産隔離機能の悪用です。そのため新信託法においては、自己信託は公正証書によってのみ成立させることとしています。悪質なケースでは、債権者が詐欺行為取消権をわざわざ行使させなくても、強制執行が認められることになりました。また、公益を確保すべく、自己信託を裁判所の命により終了できるという措置も講じられています。
そもそも自己信託は、高齢により判断能力が衰える前に、財産の継承者を指定する方法として検討されています。認知症対策として有効に活用することと同時に、タイミングの見極めが重要になってきます。
- 民事信託の基礎知識
-
- 民事信託の基礎知識
信託を活用すると税金が発生するパターンとは? 家族信託を活用する際には、税金を考える必要があります。最終的な税務リスクは顧問の税理士や税務署へご相談ください。ここでは、一般的な信託に関する税金のお話しをしましょう。
信託財産に不動産が含まれていると、所有権移転登記が行われるため、登記簿に受託者の氏名が記載されます。しかし、登記簿上の所有者が形式上、受託者に名義変更がなされただけでも、税金が課税されるのでしょうか?
信託設定時における税金は二つの考え方があります。
①自益信託
まず、「委託者」=「受益者」が同一人物であるのかないのか、が問題となります。
「委託者=受益者」の場合には、受益者は利益を受けている訳ではないので、贈与税は課せられません。②他益信託
委託者≠受益者の場合、つまり両者が異なる場合には、みなし贈与とみなされて贈与税が課せられます。
また、どちらの場合にも、課税されるのが、所有権移転登記の手続き時に発生する登録免許税です。
そして受託者への不動産取得税は、形式的な所有権移転のため発生しません。
同時に、委託者への譲渡取得税も利益発生が起こらないため課税されません。では、受託者に課税される税金はあるのか?
それは、毎年1月1日の不動産所有者に課せられる固定資産税です。形式的に所有者になるため、受託者に固定資産税が課税されます。しかし、実質的には信託財産の中から実務として受託者が支払いをするため、負担者は信託財産から支払うケースが多いです。
- 民事信託の基礎知識